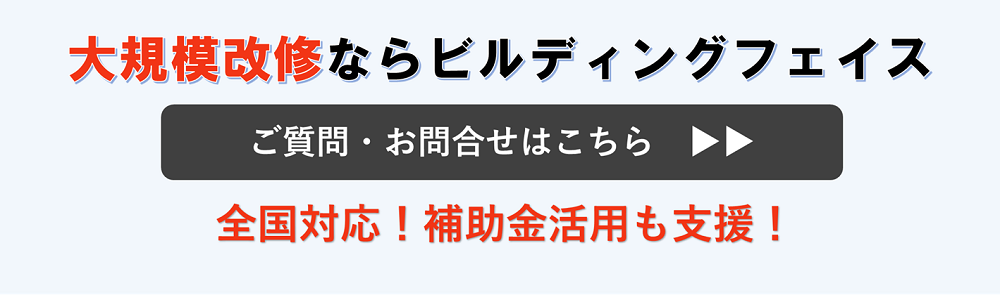大規模修繕工事にかかる期間は?工事の流れや工期短縮のコツを解説【ビルオーナー向け】
ビルやマンションの大規模修繕を計画する際、「工事期間はどれくらいかかるのか」と不安に感じるオーナーも多いでしょう。
工期が長引けば入居者やテナントへの影響も大きくなります。この記事では、規模別の工期目安や工事の流れ(準備から完了まで)、各工程にかかる時間を解説します。
さらに、工期短縮の方法や最適な時期、住民・テナントへの配慮点も紹介します。初めての方にも分かりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
大規模修繕工事の期間
大規模修繕の工期は、建物の規模や修繕内容によって異なりますが、一般的に、工事開始から完了まで数ヶ月~1年ほどかかります。
さらに、調査・計画・業者選定・合意形成といった準備期間を含めると、着工までに1~2年を要することもあります。以下に、建物の規模別の工事期間の目安を紹介します。
1. 小規模マンション(50戸未満)
工期:約3~4ヶ月
建物の規模が小さいため、修繕範囲が限られ、比較的スムーズに進行します。足場の設置・解体や外壁補修も少なく、工期は短め。ただし、居住者同士の距離が近いため、工事の周知や説明を丁寧に行い、トラブルを防ぐことが大切です。
2. 中規模マンション(50~100戸)
工期:約4~6ヶ月
建物が大きくなるにつれ、外壁・屋上・共用部分の修繕範囲が広がり、作業量や費用も増加します。管理組合での合意形成に時間がかかることが多いため、事前に十分な協議を行い、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
3. 大規模マンション(100戸以上・団地・タワーマンション)
工期:半年~1年以上
建物の高さや棟数が増えるほど、足場設置・外壁塗装・防水工事などの作業時間が長くなり、工期が1年以上に及ぶこともあります。また、管理組合での調整やタワーマンション特有の工法検討などに時間を要するため、計画段階から専門会社と連携し、無理のない工程管理を行うことが成功の鍵となります。
大規模修繕の期間は建物によって異なりますが、「自分のビルならどのくらいかかるの?」と気になっているオーナー様も多いはず!そんな時は、専門家に相談してみませんか?
ビルディングフェイスでは、建物の規模や状態に合わせた最適な工事計画をご提案。無料相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
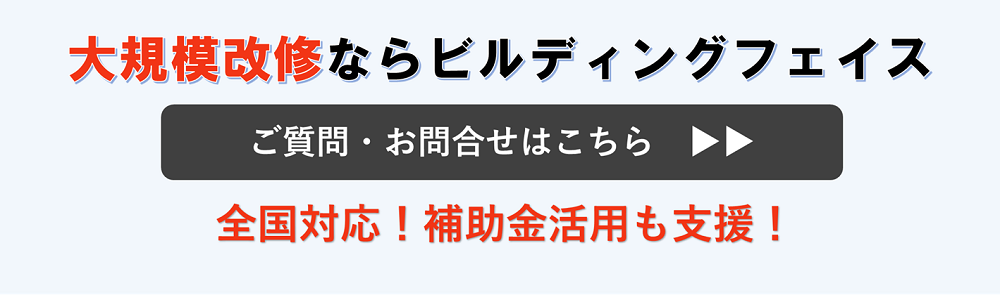
各工事にかかる期間
大規模修繕工事は複数の工程に分かれ、それぞれに一定の期間が必要です。建物の規模によって変動しますが、一般的な工期の目安を紹介します。
1. 足場・仮設設備の設置(約2~4週間)
工事の第一歩として、建物全体を囲む足場を組み、安全ネットで覆います。加えて、作業員の詰所や仮設トイレ、資材置き場、照明なども設置します。
- 小規模(50戸未満):約10~15日
- 中~大規模(50戸以上):約20~30日
建物の形状が複雑な場合や高層階の足場設置には、さらに時間を要することがあります。足場設置前には、近隣住民や入居者への工事説明を済ませることが重要です。
2. 下地補修・シーリング工事・鉄部塗装(約2週間~1ヶ月)
建物の劣化を補修し、防水性や耐久性を高める工程です。
- 所要期間:約15~30日
【主な作業内容】
| 作業 | 内容 |
| 下地補修 | 外壁のひび割れや鉄筋の露出を修繕 |
| シーリング工事 | 窓枠や外壁の継ぎ目を新しいシーリング材へ打ち替え |
| 鉄部塗装 | 手すり・階段・配管のサビ除去と再塗装 |
これらの作業は同時進行することが多く、劣化の程度によって工期が前後します。
3. 外壁塗装・防水工事(約1~3ヶ月)
下地補修が完了したら、建物の保護と美観向上のための塗装・防水施工を行います。
- 小規模(50戸未満):約1ヶ月
- 中~大規模(50戸以上):約2~3ヶ月
【主な作業内容】
| 作業 | 内容 |
| 外壁塗装 | 下塗り・中塗り・上塗りの3回塗装で耐久性を強化 |
| 防水工事 | 屋上・バルコニー・共用廊下の防水層を更新 |
塗装や防水作業は乾燥時間を要するため、天候に左右されやすく、雨が続くと工期が延びることもあります。
4. 足場解体・仕上げ(約1週間)
塗装・防水が完了したら、足場を解体し、建物周辺を清掃。
- 所要期間:約3~7日
その後、最終点検を経て工事が完了します。
ポイント整理
各工程の工期を合わせると、大規模修繕の全体期間は数ヶ月~1年程度となります。規模が大きいほど工期も長くなり、特に天候の影響を受けやすい工程では余裕を持った計画が必要です。
大規模修繕工事は何年ごとに行う?
大規模修繕工事の実施時期は、建物の構造・立地条件・管理状態によって異なります。しかし、一般的には12~15年周期で実施するケースが多く、このタイミングで修繕が推奨される主な理由は以下の通りです。
1. 建築基準法の規定
外壁がタイル貼りのマンションは、築10年を超えたら3年以内に全面打診調査を実施する義務があります。この調査結果をもとに、劣化状況を確認し、12年前後を目安に修繕を計画することが一般的です。
2. 経年劣化の進行
築10~15年で、以下のような劣化が顕著になります。
- 外壁のひび割れやタイルの剥離
- 鉄部のサビや塗装の剥がれ
- シーリング材(コーキング)の劣化
- 屋上防水層の耐用年数(約10~15年)
これらの劣化が進むと、建物の安全性が低下するため、早めの修繕が必要です。
3. 修繕積立金の計画
多くの管理組合では、修繕積立金の積み立てペースに合わせ、12年ごとに大規模修繕を計画しています。適切な周期で実施することで、急な修繕費の負担を防ぎ、資産価値を維持できます。
ポイント整理
大規模修繕は、12~15年周期が目安ですが、建物の状況により前後することもあります。定期的な点検と計画的な修繕が、建物の長寿命化と安全性確保につながります。
関連記事:マンションの大規模修繕で周期の違いがあるのはなぜ?12年?15年?18年?
大規模修繕の流れ:準備から完了までの9ステップ
大規模修繕工事は、施工前の準備から完了後のフォローまで、いくつものステップを踏んで進められます。大規模修繕工事の大まかな流れを解説します。
ステップ1:大規模修繕委員会の結成
まずは、大規模修繕を主導する修繕委員会を立ち上げます。
- マンションの場合:管理組合の有志メンバーで構成
- ビルオーナーの場合:物件管理担当者や協力者でチームを結成
修繕計画の立案、業者選定、入居者対応などを担当し、専門知識がない場合は管理会社や修繕コンサルタントのサポートを受けながら進めると安心です。
ステップ2:建物調査診断の実施
現状を正確に把握するため、専門業者による建物診断を実施します。
【調査内容】
- 外壁や屋上、防水層、鉄部、設備機器の劣化状況の確認
- 打診調査(外壁タイルの浮きチェック)
- 赤外線調査(内部劣化の可視化)
- コンクリート中性化試験(鉄筋の劣化診断)
調査結果をもとに修繕が必要な箇所を洗い出し、工事範囲と内容を明確にします。劣化が軽微なら工事を最小限に抑えられますが、想定以上のダメージが発見されることもあるため、専門業者に依頼し、正確なデータを取得することが重要です。
ステップ3:施工計画と資金計画の作成
建物調査の結果をもとに、修繕工事の施工計画と資金計画を策定します。
- 施工計画:修繕箇所、工法、使用材料、工事の優先順位、工程表(スケジュール)を決定
- 資金計画:概算費用を算出し、必要な資金の調達方法を検討
マンションでは修繕積立金が主な財源ですが、不足する場合は一時金の徴収や金融機関からの借入れを考える必要があります。ビルオーナーの場合も、修繕予算の範囲で対応するか、金融機関の融資を活用するかを判断します。
計画策定には、建築コンサルタントや管理会社の技術者を交え、建物に適した工法やコストバランス、長期的なメンテナンス計画まで考慮することが重要です。策定した計画は委員会内で共有し、関係者の合意を得ることでスムーズな進行につながります。
ステップ4:施工業者の選定
施工計画がまとまったら、工事を請け負う業者を選定します。
- 複数の業者から見積もりを取得し、比較検討するのが一般的
- マンションの場合:管理組合で入札やプロポーザルを実施し、公正に選定
- ビルオーナーの場合:ビルメンテナンス会社や専門工事会社から相見積もりを取得
業者選定では、価格だけでなく、工事内容の提案、実績、工期の見通しを重視します。費用が安くても実績が少ない会社より、経験豊富で信頼できる業者を選ぶ方が、結果的に満足度の高い工事につながるため慎重に判断しましょう。
また、住民向けのプレゼンテーションを実施し、透明性のある選定プロセスを設けることでトラブルの防止にもつながります。
ステップ5:施工計画および資金計画の再確認と見直し
施工業者が決まったら、当初の施工計画・資金計画を最終確認・見直しします。
- 業者から詳細な工事提案書、工程表、見積書を受け取り、委員会やオーナー側で精査
- 工事内容に過不足がないか、見積金額が予算内に収まっているか、工期に無理がないかを確認する
計画と実際の見積もりに差がある場合、工事項目の調整、工期の短縮、費用の削減などを業者と協議します。特にマンション管理組合では、総会での決議前に計画を精査し、合意形成を図ることが重要です。
この段階で、工事の詳細や進行方法に関する認識を委員会や関係者全員で統一し、「この計画で進める」と確定させることが、スムーズな着工につながります。
ステップ6:工事説明会・総会の開催と決議の実施
工事計画と施工業者が決まったら、入居者や関係者に向けた工事説明会を開催し、詳細を周知します。
- マンションの場合:管理組合主導で説明会を開き、修繕委員会や施工会社から工事の内容、スケジュール、影響範囲を説明
- ビルの場合:テナントや利用者向けに事前説明を実施
この場で質疑応答を行い、住民や利用者の不安を解消することが重要です。
マンション管理組合では、説明会後に臨時総会を開催し、修繕工事の実施を正式に決議します。
- 議決内容:工事の実施、予算の確定(修繕積立金の使用、一時金徴収の有無など)
- 決議方法:区分所有法に基づく特別決議(通常、議決権総数の4分の3以上の賛成が必要)
事前の合意形成がしっかりできていれば、スムーズな承認につながります。住民やテナントの協力を得るためにも、説明は丁寧に行うことが大切です。
7. 施工会社と契約
総会で工事が承認されたら、選定した施工会社と工事請負契約を締結します。
【契約内容の確認項目】
- 工事範囲・仕様
- 工期とスケジュール
- 工事費用と支払条件
- 緊急時の対応ルール
- アフターサービス・保証期間
契約前に、工期や支払いスケジュール、保証内容を再確認し、必要に応じて修正を加えます。
また、工事期間中の住民向け連絡体制(現場監督や窓口担当の情報)や、工事日誌の共有方法も事前に決めておくと、トラブル防止につながります。
ステップ8:工事の実施
契約後、いよいよ大規模修繕工事が着工します。
【工事の進行プロセス】
| 工事工程 | 作業内容 |
| 1.足場仮設 | 建物全体を囲い、安全対策を実施 |
| 2.下地補修 | ひび割れ・劣化部分を修復 |
| 3.塗装・防水 | 外壁塗装や屋上・バルコニーの防水工事 |
| 4.足場解体 | 清掃・最終チェック後、足場を撤去 |
工事期間中は、定期的に工事進捗会議を開催し、修繕委員会やオーナーと施工会社で状況確認や課題の共有を行います。
【重要な対応事項】
- 騒音が発生する作業や断水など、入居者・テナントに影響のある工事は事前通知を徹底
- 苦情や問い合わせには迅速に対応し、トラブルを未然に防ぐ
- 想定外の不具合が発見された場合(構造部の劣化など)は、修繕委員会と施工会社で協議し、追加工事の要否を判断
工事完了後は、竣工検査を実施し、不備がないか最終チェックを行います。マンションでは管理組合や修繕委員会が、ビルではオーナーが立ち会い、施工会社とともに仕上がりを確認します。
第三者監理のコンサルタントがいる場合は、専門家による検査を加えると、より精度の高いチェックが可能です。問題がなければ工事引渡しとなり、大規模修繕が完了します。
ステップ9:アフターフォロー
工事完了後も、定期点検やアフターフォローを計画することが重要です。
- 保証期間の確認:施工箇所ごとに設定(例:防水工事は10年保証など)
- 定期点検の実施:工事完了後1年・2年後に無料点検を行う施工会社も多い
- 入居者・テナントからの問い合わせ対応:工事後の不具合は施工会社に迅速に連絡し、対応してもらう
また、修繕工事の記録(報告書・写真・支出金額など)を保管し、次回の修繕計画に活かします。大規模修繕は一度で終わるものではなく、定期的な実施が必要なため、今回の経験を次回の計画に反映させることが建物の維持管理に役立ちます。
「どの業者に頼めば安心?」「計画の進め方がわからない…」そんなお悩みはありませんか?大規模修繕を成功させるには、専門会社のサポートを活用することが重要です。ビルディングフェイスでは、計画段階から施工完了までしっかりサポートし、効率的かつ確実に工事を進めるお手伝いをいたします。失敗しない大規模修繕を実現するために、ぜひ当社のサービスをご活用ください。
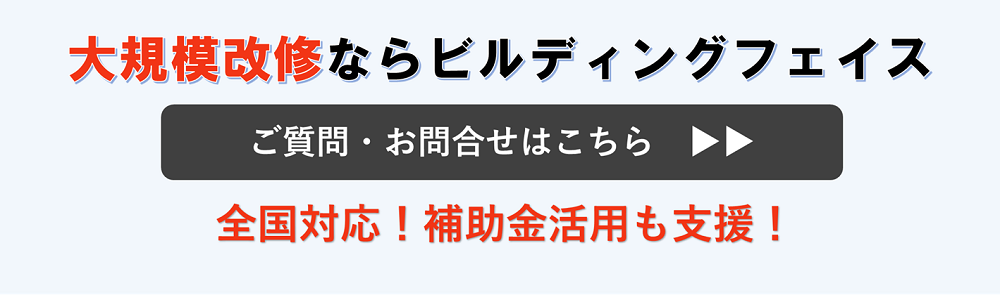
関連記事:大規模修繕工事の流れと進め方を解説!周期や費用、成功させるポイントを紹介
工事期間を短縮する方法
大規模修繕は規模が大きいほど工期が長くなりますが、適切な工夫で短縮可能です。工期を抑えることは、入居者やテナントの負担軽減やコスト削減にもつながります。ここでは、工事期間を短縮するための具体的なポイントを紹介します。
1. 効率的なスケジュール管理
工期を短縮するには、綿密な工程管理が不可欠です。信頼できる施工業者を選び、無駄のない工程表を作成しましょう。例えば、足場設置後に各側面の下地補修を同時進行させたり、屋上防水と外壁塗装を別班で同時施工することで、全体の工期を短縮できます。
ただし、安全性や品質を確保するために、過度な短縮は避けるべきです。オーナーや管理組合は、定期的に進捗を確認し、遅れが生じた際は迅速に対策を講じることが重要です。
2. 事前調査と準備の徹底
着工前の準備を万全にすることで、工期短縮が可能になります。まず、建物診断を徹底し、修繕が必要な箇所を事前に特定することで、追加工事のリスクを削減します。
また、管理組合の合意形成を早期に完了させることで、意思決定の遅れによる着工の遅延を防ぐことが重要です。
さらに、足場設置届の提出や近隣挨拶などの行政手続き・調整を事前に済ませておくことで、スムーズな工事進行が可能になります。計画段階で不確定要素を排除し、着工後の手戻りを防ぐことが工期短縮のポイントとなります。
3. 天候や季節を考慮した計画
大規模修繕は天候の影響を受けやすいため、工期を最適化するには季節要因を考慮したスケジュール管理が欠かせません。梅雨や台風シーズンを避けることで、雨天による足場作業や塗装の中断リスクを軽減できます。
また、工期内に2週間程度の予備日を設定し、天候不良時の調整期間を確保することも有効です。特に寒冷地では、低温による施工制限を考慮し、保温養生対策を講じることが重要になります。天候リスクを最小限に抑え、計画通りに工事を進めるためには、事前の調整と柔軟な対応が求められます。
ポイント整理
工事期間を短縮するには、工程管理の最適化、事前準備の徹底、天候リスクの考慮が不可欠です。計画段階から余裕を持ち、無理のないスケジュールを組むことで、効率的な工事進行が可能になります。
工事をスムーズに進めるには、経験に基づいた段取りと優れたマネジメントが欠かせません。
ビルディングフェイスでは、スケジュール管理のプロが工期短縮のご提案から現場管理まで一括対応!オーナー様の負担を軽減し、工事をスムーズに完了へ導きます。「できるだけ早く工事を終わらせたい!」とお考えなら、ぜひビルディングフェイスにご相談ください。
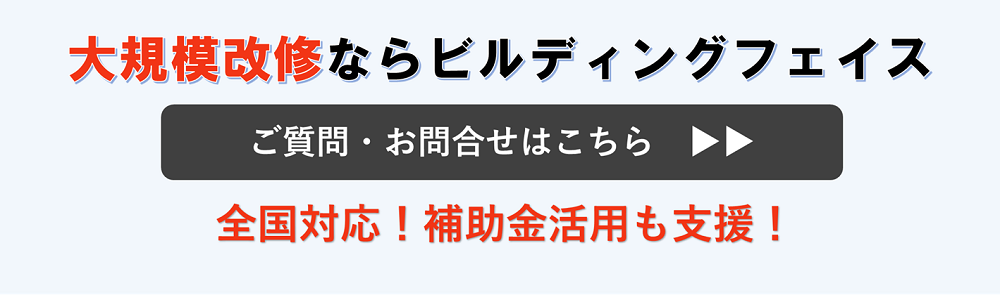
大規模修繕に適した季節
大規模修繕の工期は気候条件に大きく左右されるため、適した時期を選ぶことが重要です。天候が安定している季節を選ぶことで、スムーズな進行と高品質な施工が期待できます。
一般的に春(3~5月)と秋(9~11月)が適しているとされています。その理由と注意点を解説します。
春・秋が最も大規模修繕に適している
春(3~5月)と秋(9~11月)は、気温や湿度が安定し、屋外工事に適した季節です。主な理由は以下の4つです。
- 気候が穏やかで作業効率が向上:暑さや寒さが少なく、職人の作業がしやすい。塗料や防水材の乾燥・硬化にも適しているため、施工品質が安定する。
- 降水量が少なく工期が遅れにくい:梅雨や台風シーズンに比べて雨が少なく、中断が発生しにくいため、計画通りに進みやすい。
- 日照時間が十分にある:明るい時間が長いため、作業時間を確保しやすく、効率的に工事を進められる。
- 居住者の負担が少ない:真夏の足場やシートによる室温上昇、冬の冷え込みの影響を受けにくく、入居者の快適性が保たれる。
ただし、秋は台風シーズン(9月)に注意が必要です。台風の影響で工事が一時中断する可能性があるため、予備日を確保しておくと安心です。春はゴールデンウィーク期間の騒音対策も考慮しましょう。
梅雨・冬季の工事リスクと対策
梅雨(6~7月)や冬季(12~2月)の工事は、天候の影響を受けやすいため、慎重な計画が必要です。
梅雨・台風シーズン(6~9月)のリスクと対策
| リスク | 対策 |
| 長雨で外壁塗装やシーリング工事ができない | 工期に余裕を持たせ、雨天による遅延を考慮したスケジュールを組む |
| 台風の影響で足場作業が中断する可能性 | 梅雨前に外壁塗装を完了させるなど、天候を考慮した工程調整を行う |
| 工事中断が続くと工期が大幅に延びる | 室内や共用部の補修など、天候に影響されない作業を雨天日に割り当てる |
冬季(12~2月)のリスクと対策
| リスク | 対策 |
| 降雪や凍結で作業が中断する | 凍結リスクの高い期間を避けるか、保温養生を実施する |
| 低温により塗料やコンクリートの施工に支障が出る | 施工可能な温度を考慮し、作業の優先順位を調整 |
| 工事の進行が天候に左右される | 資材調達や職人の休養日を天候不良の日に充て、好天時に作業を集中させる |
ポイント整理
最適な工期を確保するには、春・秋の工事が理想的です。ただし、やむを得ず梅雨や冬に工事を行う場合でも、工程の工夫や柔軟な対応によってリスクを最小限に抑えることが可能です。適切な時期選びと対策を講じることで、スムーズな大規模修繕を実現できます。
大規模修繕期間中の住民・テナントへの影響と対応策
大規模修繕工事中、住民やテナントの生活や業務にさまざまな影響が及びます。ビルオーナーは、これらの支障を事前に把握し、適切な対応を取ることが重要です。主な影響と対策を整理します。
住民・テナントへの影響
| 影響 | 内容 |
| 騒音 | 足場の組立・解体、コンクリートの補修、ドリル作業などの大きな音が発生。日中在宅の住民やオフィス業務に影響 |
| 振動 | コンクリート補修や鉄部研磨の振動が建物全体に伝わり、精密機器を扱うオフィスに影響 |
| 塗料・シンナー臭 | 外壁塗装や防水工事の際、特有の臭気が発生。換気の制限が必要な場合も |
| 日照・通風の低下 | 足場のメッシュシートにより室内が薄暗くなり、通風も制限される |
| ベランダの使用制限 | 足場設置中は、洗濯物が干せず、窓の開閉がしにくい |
| 建物設備の一時停止 | 屋上防水工事で断水、電気設備の更新で停電など、一時的な制約が発生 |
| 店舗営業への影響 | 足場やシートで建物が覆われると視認性が低下し、売上減少の懸念 |
住民・テナントへの対応策
| 対応策 | 内容 |
| 事前通知の徹底 | 工事説明会や通知で、工事期間・影響(騒音・断水など)を具体的に周知 |
| 騒音・振動対策 | 工事時間を9時~17時に限定し、特に騒音の大きい作業は時間帯を配慮 |
| 臭気対策 | 低臭気の塗料を使用し、換気の推奨や事前通知を実施 |
| 安全確保 | 転落・落下防止策を徹底し、共用部に滑り止めマットや案内表示を設置 |
| 連絡窓口の設置 | 問い合わせや苦情対応の窓口を明確化し、迅速な対応を行う |
| テナント支援 | 「営業中」の掲示やサービス券配布で集客サポート |
| 工事後のフォロー | 工事完了後に感謝の意を伝え、仕上がりを説明 |
ポイント整理
大規模修繕工事は、住民やテナントにとって「負担が大きいため、事前の周知と配慮が不可欠です。誠実な対応と情報共有を徹底し、工事による影響を最小限に抑えることで、関係者の理解と協力を得ながら円滑に進めることができます。
まとめ
大規模修繕を成功させるには、事前の計画と適切な対応が不可欠です。適切な工事期間の見極め、信頼できる施工業者の選定、住民・テナントへの配慮を徹底しましょう。
また、情報共有をしっかり行い、必要に応じて専門家のサポートを活用することで、スムーズな進行と満足度の高い工事を実現できます。
建物の資産価値を維持・向上させるためにも、計画的な修繕を進めていきましょう。